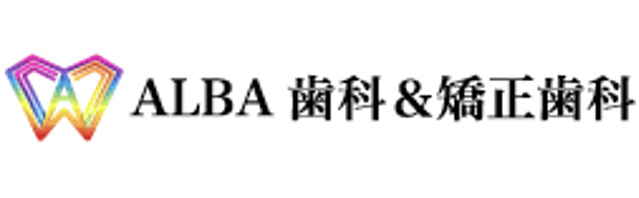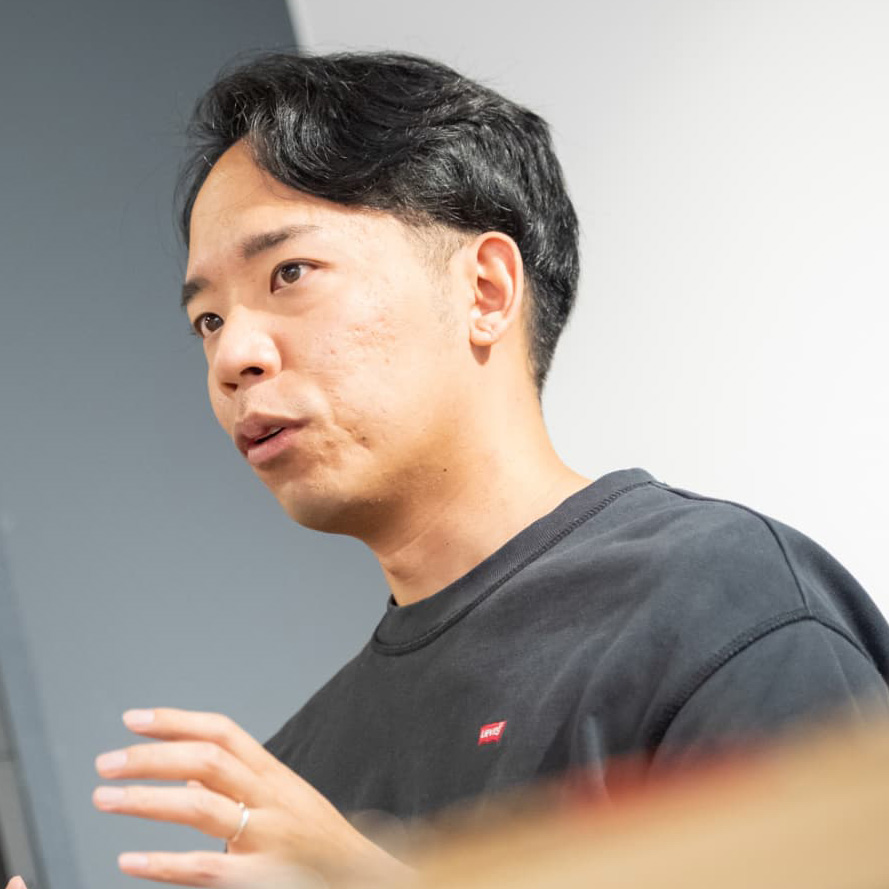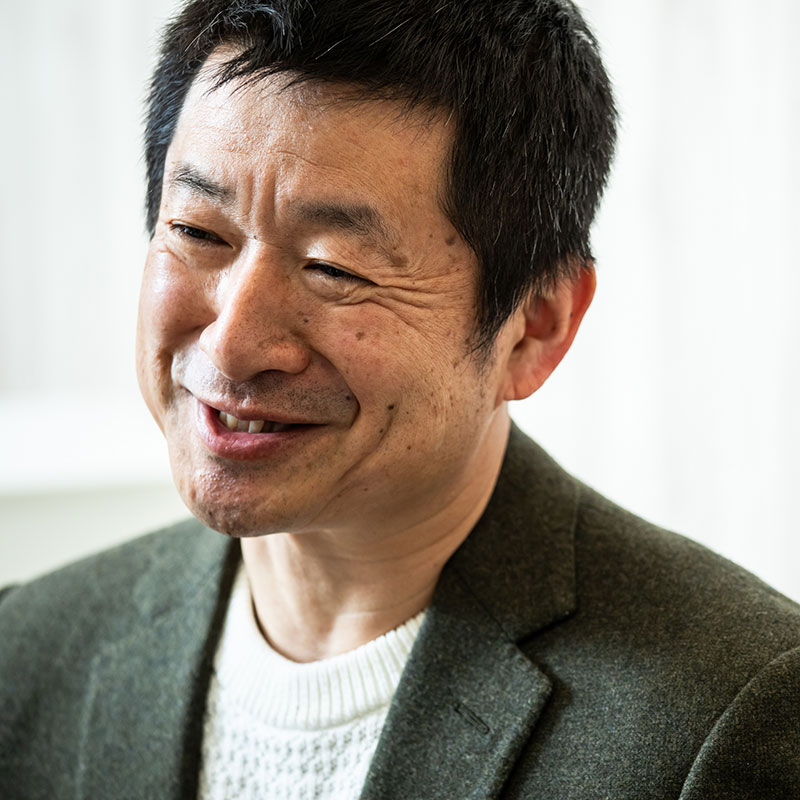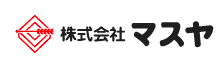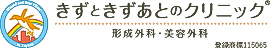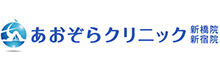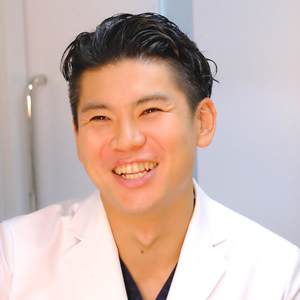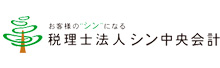CASE STUDY
「会社の未来を一緒に語れる仲間が増えた」
”社長の経営”から、“みんなの経営”へ
「会社の未来を一緒に語れる仲間が増えた」”社長の経営”から、“みんなの経営”へ

株式会社ナハト
代表取締役
安達 友基氏
代表取締役 安達 友基氏

事業内容:
”マーケットの勝者を創造する会社”を企業MISSIONに、インフルエンサーマーケティング事業やSNSを軸にしたデジタルマーケテイング事業といったWEB広告を中心に広告代理事業を展開。業界屈指のコミット力を武器に、創業4年で2,000件以上の大手企業PR実績を持つ。「ベストベンチャー100」2022にも選出
■株式会社ナハト https://nahato.co.jp
規模: 100名〜1,000名
業界: IT・通信業界
あの社長が言った「『すごい会議』、いいよ」
— 2021年11月に導入いただいたきっかけを教えてください。
メンズクリアを経営する株式会社クリア元代表の倉田さんに「『すごい会議』、いいよ」と言われて興味を持ったのがきっかけです。金額を聞いて一瞬迷ったものの、何が『いい』のかを確かめるには安いと考え、始めてみました。

— 初日のセッションDay1を実施した感想を教えてください。
セッションは地獄でした(笑)。拘束時間が10時間と長い上に、常に意思決定を迫られるのでめちゃくちゃ大変。でも、だからこそ自社の課題に気づけた。
当時は社員数が100名を超え、階層も増え、私の声が現場に届かなくなり始めたタイミング。それでも社長として、プロジェクトのボスとして、またチームリーダーとしての全役割を私が担い、私の意思決定が「会社の正義」という状態を続けていたんです。
自分がどれだけワンマン経営で会社を動かしてきたか。
改めて自覚すると同時に、私が1人で組織をけん引する“社長 対 社員100名”の体制が限界に来ていたことを自覚しました。
— 初日の10時間のセッションで、他の参加者にはどのような変化が生まれましたか。
幹部メンバー8名、オブザーブ社員が約20名という大所帯で実施するうちに、“私”ではなく「“みんなは”どうしたいのか?」という議論が生まれたことが肝でした。
互いに質問し合い、全員の総意として意思決定していくことで、“『社長』の経営”から“『みんなの』経営”へとメンバーの意識が変わった。
特に、幹部メンバーが経営を自分ゴトと捉えてくれたことで、自分たちが「経営チーム」らしくなれたような、今までにない手応えがありました。
導入の価値「“みんなでやる意味”が可視化された」
— 改めて、導入後の変化について教えてください。
大きくは3つです。まず、会社としての目標をつくれたこと。そして、“社長 対 社員”の構図から抜け出し、法人格として一つのチームになれたこと。最後に、僕を含めたメンバーに論理的思考力と言語化する力がついたこと。

— 会社としての「目標」を立てることで、どのような発見や体験がありましたか。
正直なところ、私自身も会社に対する大目標を持って経営してきたわけではなく、『昨日より今日をよくしよう』、『何かいいことを成し遂げよう』という、漠然としたイメージだけでここまで進んできました。
「売り上げ100億を目指す」という表現はしていましたが、目標というより、成長をわかりやすく表した一つの記号です。
今回、「すごい会議」で中長期目標を立ててわかったのは、目指す未来の輪郭がはっきりすると、“みんなでやる意味”が可視化される、ということ。
短期的に稼ぎたいだけなら自分一人でやればいい。そうでなく、高く遠い目標を目指すからみんなで進む意味がある。長期的な目標を意識した瞬間に、チームとして一つになれた感覚がありました。
— “みんなでやる意味”が可視化されたことで、具体的にどんな変化が生まれましたか。
現場の馬力が圧倒的に上がりました。仲の良い友人、知人と数人で始めた会社なので、彼らからすると「法人」というより私個人とつながる意識が強かったと思うんです。
その成り立ちがあるからこそ、組織が拡大しても尚、法人格としての意識が希薄で、『会社は社長のもの』『社長のための売り上げづくり』といった雰囲気が抜けきらないように感じていました。
しかし「社長のために」働くのでは、仕事へのモチベーションに限界がある。
「すごい会議」を通して自分たちで目標を決め、達成に向けて個々人がコミットしたからこそ、「みんなで目指そう!」、「自分たちの会社だ!」と、目線がそろった。
経営にかかわる意思決定を彼ら自身がしたことで、責任感と共に意欲や実行力が上がったのだと思います。
曖昧さをなくし、“言語化する”価値
— “論理的思考力と言語化”の効果についても詳しく教えてください。
私は言語化が得意ではないので、「なんかこの広告イケてるよね」といった非常に主観的で感覚的なコミュニケーションをしがちでした。と同時に、それが会社の文化でもあったんです。
しかし、曖昧さを含んだコミュニケーションを100名の組織で使い合えば、100通りの解釈と正義がぶつかり始めます。認識がズレるのも無理はない。
この規模を効果的にマネジメントするには、「すごい会議」のロジカルな思考やルールに基づいた言語化が必要だと実感しました。私自身にとって大きな学びであり、成長させてもらいましたね。
「すごい会議」では、明確に言語化してコミットメントに落とします。誰がどう見てもズレなく認識できるよう因数分解して共通言語化し、管理する。組織の規模を拡大するタイミングには不可欠です。
一方で、言語で固めすぎないユニークなコミュニケーションも、ナハトさん“ならでは”の大切なカルチャー。場面に応じてコミュニケーションを選択し、使い分けていくことをおすすめします。

— 「言語化」を意識した結果、以前と比べてどんな“違い”が生まれましたか。
今まで動かなかったものが、“動く”ようになりましたね。
これまでは『これだけ伝えたのに、なぜ現場はやらないんだろう?』と、いらだちを感じることもありましたが、「すごい会議」のマネジメント手法を学び、私にも原因があったと理解できた。
主担当者や責任、行動内容や納期を明確に言語化し、「期待を合意」していなかったことが原因の一つ。今では、現場が実行しやすいサイズ感を理解した上で私自身が指示できるようになりました。
一方で、誰にでもわかる言葉を使いすぎても、心に響かず、熱量が上がらないのも真実。『この人と働きたい』と、周囲をノセるコミュニケーションが私の強みなので、どちらも大切にしていきます。
“人”を育てる3つの事業部別プロジェクト
— 経営チーム以外にも、事業部別の「すごい会議」プロジェクトを3チーム立ち上げたとお聞きしました。目的や期待を教えてください。
経営チームとしての意思統一はできたものの、事業部内で見るとまとまりの弱い状態。幹部メンバーだけでなく、現場社員を巻き込んで一体感を強めるべく、「すごい会議」のプロジェクト数を増やしました。
具体的な狙いは、責任者としての事業部長の育成と、一人でも多くの社員をポジティブに問題解決できる“問題解決人材”へと育成することです。
「すごい会議」の思考やフォーマットを浸透させ、現場の人材力、組織力を底上げしていきます。
事業部ごとにKPIが異なるので、問題解決の視点から見てもプロジェクトを事業部別に走らせる構造は理にかなっています。
安達さんからの「短期集中でなく、長期にわたってかかわり続けてほしい」というリクエストに応え、「すごい会議」流の思考や行動を中長期で組織に広く浸透させるプランです。

— 現場のみなさんの成長を、どのように実感しますか。
まずは発言内容。「これは解釈ですが」「事実としては」と、現場のスタッフが「すごい会議」流の発言を自然とするようになりました。また、事業部長も自分の意見をしっかり持って発信できるようになり、現場での私の意思決定は大きく減っています。現場を任せられていることがうれしいですね。
私が思うに、「すごい会議」の本質は、思考や方法を習慣化することで、“人”が成長すること。重要なのは会議そのものでなく、会議の場を使って個人の思考力や問題解決力を上げることにあると理解しています。
“人”の成長で組織の成長を確かにできるのが、この会議の最大の価値です。
社長に「問い」を投げかける、コーチの存在
— 安達社長が感じる、久保田コーチの魅力をお聞かせください。
久保田さんは、経営知識が豊富な上に、「すごい会議」ルールを全うしながらも柔軟に最適化してくれる点がいいんです。感覚派の私にロジカルな質問をくれる点も助かっていて、この会議で一番変化しているのは私自身だと自負しています。
さらに、第三者として嫌われ役を担ってくれることも魅力の一つ。
私が思うに優秀なマネジャーとは、3つの要素を使いこなす人材。①目標に向けて部下のモチベーションを上げるポジティブな側面、②正しくフィードバックして修正させる、どちらかというとネガティブな側面、③最終的に評価するリアルな側面、です。
本来は私がそれを体現するべきですが、その三役を全社規模で全うするのは物理的にも困難。厳しくフィードバックしてくれる、ネガティブ担当の久保田さんがいることで、私はいい面に専念できます(笑)。

“100億円企業”になるより大切なこと
— 導入して1年弱、安達社長にとって“一番うれしい変化”とは何でしょうか。
会社の未来を一緒に語れる仲間が増えたことです。単に“100億円企業”になっても私には意味がなく、“誰と、どう成長して成果を残せるか”が、何より重要。
高い山を踏破することがうれしいのでなく、山道を登りながら後ろを振り返ったときに、「こんなところまで登ってきたな」と、語れる仲間がいることに幸せを感じます。
幹部メンバーの経営意識が圧倒的に高まり、同じ目線で語れる仲間が増えたこと、それが最大の喜びです。

— 印象に残る問題解決があれば教えてください。
個人的には、雨でゴルフが中止になったときに朝食をご一緒したことが印象に残りました(笑)。
仕事でも会議でもない場ですが、「すごい会議」のメソッドを使って身近な問題解決を実践した記憶があります。
私の後輩の個人的な悩みを「すごい会議」の問題解決のフォーマットで解決してもらいましたね。
フォーマットを使えば大抵のことは解決策が見つかるとわかり、非常に興味深い発見でした。例え一人では答えを見つけることが難しくても、ルールに沿ってガイドしてくれる久保田さんがいれば、ブレずに進める。その価値を再実感しました。
なぜ、「すごい会議」は必要とされ続けるのか
— 「すごい会議」の必要性を感じるのはどんなタイミングですか。
実は、『ある程度うまくいっているから、もう必要ないかも』と思う瞬間があるんです。ところが、いざ会議を始めると新しい問題が出てくるので、やはり必要だと思い直す。その繰り返しです。
緊急性の高い問題は解決が済んでいて、“緊急性が低いけれど重要な問題”に取り組めているからこそ発生する現象ですね。表出していない問題も、目標とのギャップを問われることで姿を現し始める。
問題を積極的にあぶり出し、早期につぶすことで成長のスピードは確実に加速します。

— 導入時の期待に対して、現在の満足度は何%でしょうか。
100%、満足しています。「すごい会議」は、一生必要なサービスかと問われると、私が言うには違います。けれど、組織や事業を成長させたいタイミングには効果絶大。
今は複数の新規事業を立ち上げている最中なので、その事業規模や問題の内容に合わせながら「すごい会議」をチューニングして成長へと活用し続けます。
「振り返って一緒に語れる仲間こそ、宝」
— 今後のビジョンとして、安達さんが目指す世界観を教えてください。
私は、この会社を一つの村や町みたいなものだと捉えています。
社会にインパクトを与えたいという思いも、100億、1,000億という看板が必要なこともわかる。でも私にとって大切なのは、この村、町が豊かで住人が幸せであること。
そのために、経済的に勝ち続けるだけの“世の中に必要とされるプロダクト”は絶対に必要だし、住人が切磋琢磨して成長できる環境も不可欠。それを備えてこそ、周囲からも『住みたい』と思われるいいコミュニティがつくれる。
私たちなりの正義と理想でこの組織を繁栄させていくために、今あるWEBマーケティング事業を完璧なものに仕上げ、どんなビジネスをも生みだせる基盤を整えていきます。
シェアオフィスの狭い一室から始めた起業当時を思うと、“今”があることが純粋にうれしく、昔を振り返れる仲間こそ、最大の宝。今いる社員には誰一人としてほしくないのが本音です。

— ありがとうございました。
( 2022年10月)
CASE STUDY
もっと見る